燈籠
石灯籠の起源は本来仏教の献灯にあると考えられています。
仏前に灯をともし置いて、仏に供えたのもであり、もともとは中国にあったもので仏教とともに入って来たと考えられています。
奈良時代をへて、平安時代になると、寺院への献灯だけでなく、神社への献灯にも燈籠が用いられました。
室町時代には、茶道が確立し、それがまず照明と添景のため、露地に取り入られるようになりました。
茶庭から始まった石燈籠は、やがて他の様式の庭にも用いられるようになり、「用と美」の兼用で用いられていた物が、書院式庭園のように単なる装飾物として使われるようにもなりました。
石灯籠は「立燈籠」,「生込み燈籠」,「脚付き燈籠」,「置燈籠」に大別されます。
また、燈篭の名称には、下記のように分類することもあります。
- 献灯された社寺の名によるもの。(平等院型,勧修寺型,善導寺型,般若寺型など)
- 在存する位置によるもの。(神前型,お間型など)
- 形状によるもの。(四角灯籠,六角灯籠,八角灯籠など)
- 茶人の名をつけたもの。(利休型,織部型,遠州型など)
- 用途によるもの。(道しるべ型など)
- 形を象徴するもの。(草屋型,蛍燈籠,三光燈籠など)
燈籠(とうろう)は灯籠、燈篭、灯篭とも表記されることがあります。
石灯籠には、型の類似品は多く見られるけれども、その源泉となっている灯籠を本歌といいます。
通常、石灯籠の大きさは尺寸単位の高さで示されますが、雪見燈籠は例外的に笠の直径で示します。
燈籠 の種類
- 『六角形』
-
 通常円形である竿以外の部分の平面形が六角形で、春日燈籠とも通称される最も多く見られる燈籠。
通常円形である竿以外の部分の平面形が六角形で、春日燈籠とも通称される最も多く見られる燈籠。
- 『四角形』
-
 平面形が四角形で、神社でよく見かけるもの。
平面形が四角形で、神社でよく見かけるもの。
- 『八角形』
-
 六角型よりも起源が古いと考えられている燈籠で、平面形が八角形のもの 。
六角型よりも起源が古いと考えられている燈籠で、平面形が八角形のもの 。
柚ノ木型, 当麻寺型など - 『生込み形』
-
 基礎の部分が欠如し、その代わりに竿の部分を直接地中に埋め込んで据えられたもの。
基礎の部分が欠如し、その代わりに竿の部分を直接地中に埋め込んで据えられたもの。
- 『脚付形』
-
 基礎が欠如した代わりに、竿の部分が1本から数本の脚へと変形したもの。
基礎が欠如した代わりに、竿の部分が1本から数本の脚へと変形したもの。
- 『置燈籠』
-
 基礎と竿が欠如し、地上や石の上に直接置く形式となったもの。
基礎と竿が欠如し、地上や石の上に直接置く形式となったもの。
岬燈籠,寸松庵型,三光燈籠,草屋型など - 『改造形』
-

寄燈籠, 山燈籠(化燈籠)など - 『石 塔』
-
 石塔とは、石つくりの塔で、もともとの目的は、釈尊の遺骨、爪髪、歯牙、鉢衣などを埋蔵したり、霊域を記念するためのものであった。
これが、のち桃山時代になってから、一種の装飾品として庭園に置かれるようになりました。
石塔とは、石つくりの塔で、もともとの目的は、釈尊の遺骨、爪髪、歯牙、鉢衣などを埋蔵したり、霊域を記念するためのものであった。
これが、のち桃山時代になってから、一種の装飾品として庭園に置かれるようになりました。
多層塔,五輪塔,多宝塔,宝篋印塔,卒塔婆など
燈籠 の構成部分
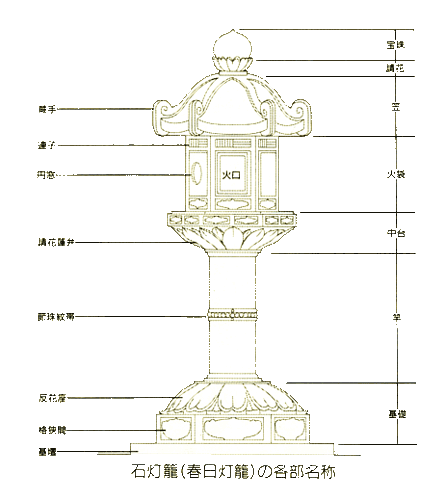
宝珠 - 笠の頂点にある葱花状の形態をした部分で、石塔や方形造りの建物の頂上にある飾りと同種のものと見られている。請花をともなったものもある。
笠 - 火袋の上の屋根に相当する部分で、四角形や六角形など、燈籠の型に応じた形態をとるのが一般である。
火袋 - 中台の上にあり、燈籠の本来の目的である点灯をするための部分で、通常1から2側面の中央部に火口が開かれている。
中台 - 竿の上にあって火袋を支える部分で、基礎をやや小ぶりにして、そのまま返して乗せたような形状をしている。
竿 - 基礎の上に立つ柱状の部分で、形態的にいうと、六角形や八角形の燈籠では、通常円柱形であるが、四角形の場合だけは、ほとんどの場合が四角形である。
基礎 - 燈籠を構成する最下部で、地輪とも称される。基礎の下には、基壇を設けることもある。竿を地中に直接埋め込む「生込み燈篭」にはない。
基壇 - 基礎を支える壇状の台石。省略される場合も多々ある。











